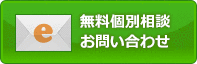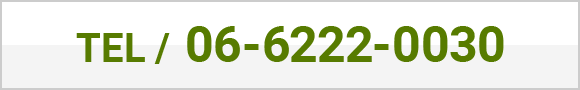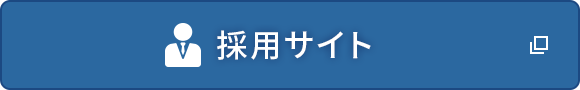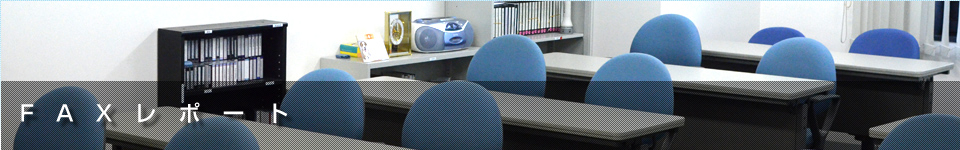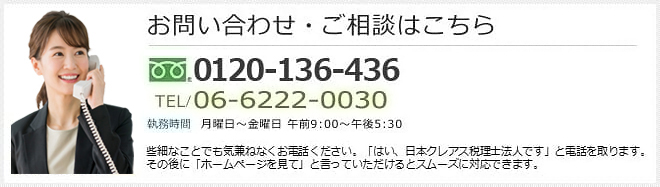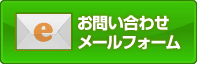ホーム > FAXレポート > 医院レポート > 医療経営情報(2019年3月14日号)
医療経営情報(2019年3月14日号)
◆妊産婦の保健・医療体制についての検討会が発足 次期改定に向け凍結された妊婦加算の代替案も議論の遡上に
――厚生労働省
妊産婦に対する保健・医療体制の在り方に関する検討会
厚生労働省は2月15日、「妊産婦に対する保健・医療体制の在り方に関する検討会」を立ち上げ、第1回会合を開催。出産年齢が上昇傾向にあることを踏まえ、妊産婦への細やかな支援が必要となっていることから、安心できる医療提供体制や健康管理のあり方について議論を進めていく。今年1月に凍結された妊婦加算についての再検討も行われる見込みで、検討結果は2020年度の次期診療報酬改定に反映されることとなりそうだ。
妊産婦の診療は、通常よりもきめ細かい配慮が求められる。近年は出産年齢が上昇傾向にあり、高齢出産の場合は特に健康管理に留意しなければならないため、産後のケアにも慎重な対応が必要だ。妊婦に対しては、検査や薬剤の処方時に胎児への影響を考慮する必要がある。女性が医療機関を受診する際の問診票には、妊娠しているかどうか確認する項目が設けられているのはそのためである。
今年1月に凍結された妊婦加算は、そうした配慮を実施している医療機関を評価するため昨年の診療報酬改定で新設された。妊娠中の女性が医療機関を受診した場合、初診料・再診料が上乗せされる仕組みで、初診の場合は75点、再診の場合は38点となる。自己負担割合が3割の場合、初診で約230円、再診で約110円増える計算だ。
この妊婦加算、実は改定直後にはさして話題にのぼらなかった。しかし、昨年秋ごろからTwitterなどのSNSで「妊婦だけ自己負担額が増えている」と不満の声が頻発。少子化対策に逆行しているとの批判も相次ぎ、マスメディアもニュースで取り上げるようになる。一連の動きを受け、今年夏に参議院議員選挙を控えていることもあり政権基盤を維持したい自由民主党が敏感に反応。厚生労働部会で「今後廃止すべき」と総意を取りまとめ、迅速に凍結へと動いたというわけである。
騒動が起きた当初は「年内に見直し」と述べるにとどまっていた根本匠厚生労働相だが、12月14日の閣議後会見で凍結を表明。中央社会保険医療協議会総会に諮問し、5日後の12月19日には凍結を了承する答申書が出されている。しかし、この問題について十分な議論がなされたとは言い難いのが実情だ。中医協からの答申書に「凍結との諮問が行われたことは極めて異例」「特別な事情に基づき実施」と記載されていることが、そのことを如実に物語っている。医療機関が、妊婦への対応に通常以上の配慮をしているのは確かな事実であり、それを評価することには何ら問題はないはず。むしろ、眼科のコンタクトレンズ処方にも妊婦加算を算定している実態こそが問題であり、要件の見直しや妊婦の受診費用への助成を手厚くするなどの対応策をとるべきだったのではないか。「妊産婦に対する保健・医療体制の在り方に関する検討会」には、そのあたりまで踏み込んだ議論が展開されるかどうかも注目される。
◆費用対効果評価の骨子が固まる 製薬協は反発
10~15%の薬価下げ止めルールも設定
――厚生労働省 中央社会保険医療協議会 総会
2月20日、厚生労働省の中央社会保険医療協議会(中医協)総会は、費用対効果評価の骨子を了承。4月から本格的に制度化されることが確定した。製薬企業72社が加盟する日本製薬工業協会(製薬協)は同日、「医薬品の研究開発・安定供給を継続していくうえで厳しい内容と言わざるを得ません」と反発する声明を発表している。
骨子には、保険償還の可否判断には用いないことや、対象の要件が明記。対象品目となるのは、有用性加算が算定された新規収載品で候補の対象となるのは年間市場規模50億円以上の品目となることなどが明記。対象品目は、有用性加算が算定されたピーク時売上高100億円以上の新規薬価収載品や、市場規模1000億円以上の既収載品が中心となる。治療法が十分存在しない希少疾患や小児のみに用いられる品目は対象外だが、年間売上高350億円以上の品目や薬価の高い品目は中医協の判断で対象になることもある。
価格調整は、増分費用効果比(ICER)に基づき、調整対象に計数をかける方法で行われる。ICERが500万円/QALY以下の場合は価格を維持し、ICERが500~750万円/QALYの場合は有用性系加算を30%、営業利益率を17%引き下げる。ICERが750~1000万円/QALYの場合は有用性系加算を60%、営業利益率を33%、ICERが1000万円/QALY以上の場合は有用性系加算を90%、営業利益率を50%引き下げる。
安定供給を確保するため、10~15%と価格下げ止めのルールも設けた。有用性加算の加算率が25%の場合は10%、25~100%の場合は(10+「当該製品の有用性系加算率(%)-25」/15)%、100%以上の場合は15%となる。加算を取得しておらず開示率が50%以下の品目は下げ止めの対象外だ。
費用対効果評価は、適正な価格設定を行うための仕組みとして2010年頃から中医協で議論が展開されてきた。その背景には、医薬品や医療機器の進化がある。高度な機能を持つ医薬品や医療機器は、価格も高額にならざるを得ない。たとえばがん免疫治療薬「オプジーボ」は、薬価収載された時点で100mg1瓶が729,849円だったため、1人あたり年間で3,500万円かかると試算されていた。医療費の高騰につながることから、社会保障費を抑制したい政府は一刻も早く導入したかったというのが本音だ。
そこで、2012年に費用対効果評価専門部会が設置され、翌2013年には中間とりまとめを報告。「経済財政運営と改革の基本方針(骨太方針)2015」で2016年度の診療報酬改定を機に試行的な導入を実施することが明記され、2016年4月から試行的導入が開始した。すでに保険収載されている13品目を対象に分析を進めてきたが、活用方法や対象品目の選定基準、評価の方法などで意見がまとまらず、本格的な導入は先延ばしにされてきた。
◆勤務医の時間外労働上限、救急病院は年1,860時間 過労死ラインの約2倍 「地域医療確保」のため
――厚生労働省 医師の働き方改革に関する検討会
厚生労働省は2月20日、「医師の働き方改革に関する検討会」で、勤務医の時間外労働の上限時間を提示。原則は年960時間、月100時間未満としつつ、救急医療機関などに勤務する医師については、「地域医療確保暫定特例水準」として例外的に「年1,860時間、月100時間未満」とする意向を明らかにした。
原則となる年間960時間は、厚労省が定める「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」に基づいたものだ。いわゆる「過労死ライン」といわれるもので、月80時間以上の時間外労働が認められる場合、脳血管疾患や虚血性心疾患の発症との関連性が強いと評価している。これを踏まえると、救急医療機関に勤務する医師を対象とする年1,860時間は、月に均すと155時間となるため、「過労死ライン」の約2倍となる。
厚労省は、1月の同会合で「年1,900~2,000時間、月100時間未満」を提示していた。これは、勤務医の労働時間データの「上位10%以上」が1,944時間だったことが根拠となっている。その後、労働時間データを再度精査した結果、「上位10%以上」が1,904時間であることが判明。それに近い数字で、12カ月で割り切れる数字ということで年1,860時間に落ち着いた格好だ。
救急医療は24時間対応が必要であるため、一般的な労働時間の感覚を当てはめてシフトを組むことができないのは確かだ。しかし、「上位10%以上」とはいえ、1カ月当たり158時間以上、1か月に20日勤務と仮定すれば1日8時間近く残業時間がある現状は異常としかいいようがない。同検討会では「上位10%以上にする明確な理由がない」と反発する意見も出ているが、切り分けのポイント云々ではなく、救急医の勤務状況そのものに危機感を抱く必要があるだろう。過酷な労働環境のため、救急専門医ないし救急病院の勤務医のなり手が少ないのも事実であり、地域の医師がローテーションで担当するといった抜本的な改革が求められるフェーズに入ってきているのではないか。