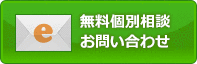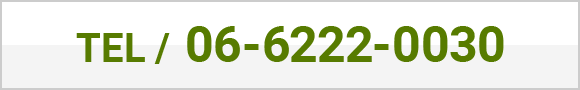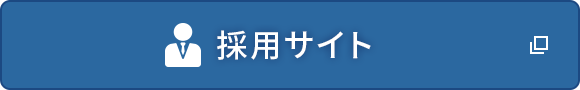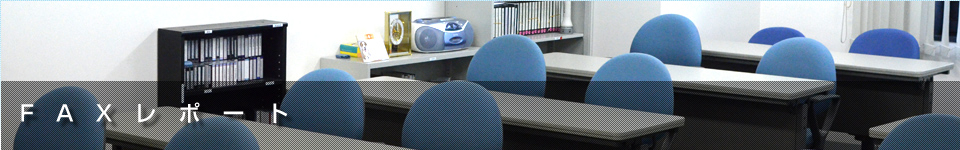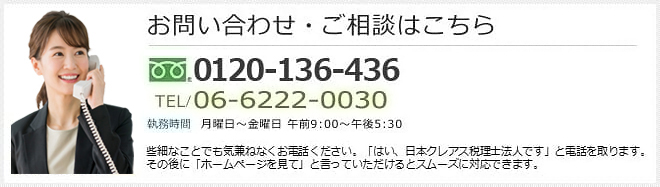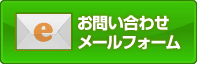ホーム > FAXレポート > 医院レポート > 医療経営情報(2019年7月18日号)
医療経営情報(2019年7月18日号)
◆厚労相 AYA世代の妊孕性温存助成制度は「検討できる段階ではない」 エビデンスが確立されていないとの判断 研究事業は今後も継続
――厚生労働省
根本匠厚生労働相は、7月16日の閣議後会見で、AYA世代の妊孕性温存のための助成制度の創設は「具体的に検討できる段階ではない」との認識を示した。妊孕性(妊娠できる力)の温存が若年のがん患者の妊娠につながるというエビデンスが十分に確立できていないことを理由に挙げている。
15~39歳のAYA世代(Adolescents and Young Adult)は、さまざまな種類のがんを発症する可能性があるとされ、年間約2万人ががんとの診断を受けている。国立がん研究センターによれば、その90%以上が20歳以上で、年代によって発症しやすいがんの種類は異なる。15~19歳では白血病やリンパ腫、骨軟部腫瘍、脳腫瘍といった希少がんが多く、30歳以上になると女性乳がん、子宮頸がん、大腸がんなどが増える。こうしたがん患者にとって、妊娠・出産は大きな悩みであり、厚労省の調査によれば25~29歳では悩みのトップとなっている。
なぜならば、抗がん剤治療や放射線治療は卵巣や精巣の働きを低下させるとされているからだ。すなわち、妊娠できる力が失われる可能性があるため、たとえば国立がん研究センターでは小児科分泌意や産婦人科、泌尿器科など生殖医療のエキスパートとネットワークを構築して妊孕性温存のための取組を行っている。がん治療開始前に精子保存や卵巣凍結保存などを行うのがそれだ。
しかし、妊孕性温存のための保存療法は保険適用外。数十万円といった費用がかかるため、経済的に断念するケースも散見される。そのため、国の助成制度を求める声があがっていた。不妊治療に関しては国の助成制度があり、1回の治療につき15万円(凍結胚移植は7.5万円)、計6回まで助成されているため(※)、当然の要望といえよう。実際、厚生労働科学研究費補助金がん対策推進総合研究事業による「小児・若年がん長期生存者に対する妊孕性のエビデンスと生殖医療ネットワーク構築に関する研究」班のホームページでは、男性のがん患者に対して「がんの治療による妊孕性低下が予想される挙児希望の男性がん患者は,射精が可能であればできるだけ『治療開始前に精子の凍結保存』をすべき」と記載されている。
では、なぜ根本厚労相が「エビデンスが十分に確立されていない」と述べたのか。女性患者に対する前出の研究班ホームページの記載が参考になる。「がんの進展がみとめられた場合には、原疾患の治療を最優先させなければなりません」「がんの種類によっては(卵巣に転移する可能性のある白血病や卵巣がんなど)、適応とならない場合もあります」と慎重な記述に終止しており、必ず妊孕性温存ができるものではないとしている。これらをもとに、「エビデンスが十分に確立されていない」として“支出”を抑えようとしたものと思われる。
一方で、少子化問題は年々深刻度を増している。2018年の出生数は92万1,000人と過去最少。出生数ゼロという衝撃の結果となった自治体が4つもあった。安倍晋三首相は少子高齢化問題を「国難」と位置づけているが、根本厚労相の発言には、こうした現状に対する危機感が感じられない。妊娠・出産へのモチベーションを途切れさせないために、少なくとも不妊治療と同等の助成は行うべきではないか。ちなみに、若年がん患者の卵巣組織の凍結保存については、欧米を中心に約4,000例以上の症例があり、日本でも32施設が実施可能となっている。
※不妊治療は、体外受精および顕微授精において助成を受けることができる。対象となるのは「特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された法律上の婚姻をしている夫婦」「治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦」。通算助成回数は、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは6回(40歳以上であるときは通算3回)まで。精子を精巣または精巣上体から採取するための手術を行った場合は1回15万円まで助成される。ただし、2012年度以前から助成を受けている夫婦で、2014年度までに通算5年間助成を受けている場合には助成されない。
◆「応召義務は民事上の負担義務ではない」
厚労省が近く通知を発出 “モンスターペイシェント”対策になるか
――厚生労働省
社会保障審議会医療部会
厚生労働省は、7月18日の社会保障審議会医療部会で、医師法の応召義務の解釈に関する研究結果を公表。「医師が患者に対して直接民事上負担する義務ではない」ことが確認されたことや、対応できない救急患者に対して他院への紹介措置をとること、診療内容そのものと関係ないクレームを繰り返し続ける患者の診療を拒否することが正当であることなどが報告された。厚労省は、これらの内容を取りまとめ、近く通知を発出する方針。モンスターペイシェント対策としての効果も期待される。
応召義務をいかに解釈するかは、医師の働き方改革を進めるうえで大きな論点となる。そのため、従来の解釈や趣旨を整理したうえで、診療拒否に関する民事裁判例の分析を行い、適切なあり方を導き出そうと有識者による研究を行ってきた。具体的には、2018年度の厚生労働科学研究として実施。研究班の主任研究者は、「医療と法」を研究テーマとしている上智大学法学部の岩田太教授だ。
研究報告書によれば、応召義務は明治時代から罰則付きで設けられてきたが、戦後になって罰則は削除。訓示的な規定として置かれてきたという。法的な性質としては、公法上の義務ではあるものの、行政処分の実例は確認されなかった。あくまで職業倫理・規範として機能してきただけで、際限なく長時間労働を求められることは不当だとしている。
では、応召義務を考慮するうえでもっとも重要な要素は何か。報告書が示したのは、緊急対応の必要性と病状の深刻度。もちろん、医師の専門性や設備の状況なども重要だとしており、逆にいえば設備や専門性が十分でなければ、救急患者に対して他院を紹介することは正当だとしている。そのうえで、「診療時間内・外」であるかどうかを考慮すべきだとした。医師の働き方改革を進めるうえで、当然の視点だといえよう。
また、「患者の迷惑行為」「医療費不払い」といった個別ケースに対してそれぞれ言及しているのも、今回の研究報告書の特徴だ。「患者の迷惑行為」については、「診療の基礎となる信頼関係が喪失している場合には、新たな診療を行わないことが正当化される」と明記。信頼関係の喪失については、「診療内容そのものと関係ないクレーム等を繰り返し続けるなど」としており、近年増えているモンスターペイシェントを意識した項目であることがわかる。
また、未収金対策も医療機関にとっては頭を悩ませる問題だが、「以前に医療費の不払いがあったとしても、そのことのみをもって診療しないことは正当化されない。しかし、支払能力があるにもかかわらず悪意を持ってあえて支払わない場合等には、診療しないことが正当化される」と問題を整理。さらに、「保険未加入など医療費の支払い能力が不確定であることのみをもって診療しないことは正当化されないが、医学的な治療を要さない自由診療において支払い能力を有さない患者を診療しないことなどは正当化される。また、特段の理由なく保険診療において自己負担分の未払いが重なっている場合には、悪意のある未払いであることが推定される場合もあると考えられる」と具体的に記載しており、悪質な未払い患者を牽制している。これらの報告は法的な強制力を持つわけではないが、厚労省が通知することで一定の抑止力を発揮することが期待できるのではないか。
◆厚労省と観光庁、外国人患者受け入れ医療機関リストを一元化 都道府県による「適格性」審査をクリアした全国1,610施設
――厚生労働省
観光庁 外客安全対策室
厚生労働省と観光庁は7月17日、「外国人患者を受け入れる医療機関の情報を取りまとめたリスト」を公表した。従来、観光庁が公表していたリストを再整理し、都道府県によって「適格性」を審査したうえで選出された全国1,610施設が掲載されている。今後、訪日外国人向けに多言語化(英語、中国簡体字、繁体字、韓国語)し、日本政府観光局(JNTO)のホームページで公開される予定だ。
今回公表されたリストはExcelデータ。住所、電話番号、受付時間、URL、対応診療科および対応外国語、対応言語および対応可能日時のほか、外国人患者対応の専門部署、外国人向け医療コーディネーター、医療通訳者の有無、JMIP(外国人患者受入れ医療機関認証制度)の認証を受けているか、JIH(ジャパンインターナショナルホスピタルズ)の推奨を受けているかなどが記載されている。利用可能なクレジットカードやキャッシュレスサービスの欄もあるのが特徴的だ。すべての医療機関で有無がわかるようにはなっておらず、空欄となっているところも多いが、項目数が多く希望に応じてソートしやすくなっているのは評価できる。
外国人患者の受け入れに関しては、これまでいろいろなリストがあった。代表的なのが観光庁によって取りまとめられていた「訪日外国人旅行者受入れ可能な医療機関リスト」(以下、観光庁リスト)だったが、受け入れの姿勢に差があり、一元化されていないためわかりづらいのが難点だった。そこで、各都道府県が「適格性」について審査できるように厚労省が介入。観光庁と共同で一元化したリストを作成した次第だ。「観光庁リスト」は、外国人患者への診療に「協力する意志」の有無で作成されていたが、今回のリストは適格性がないと判断された場合、その医療機関の合意を得たうえでリストから削除している。今後も同様のプロセスを経て、随時リストを更新していく予定だ。
なお、今回のリストは、5月末の第1回回答締切までに提出されたデータをもとにしたもの。第1回回答締切までに提出しなかった都道府県に関しては、従来の「観光庁リスト」のまま掲載されている。9月末の第2回回答締切を経て、10月を目途にリストを更新する予定となっているため、より有効なリストとなるのはそのタイミングとなりそうだ。
◆中医協、理学療法士が多い訪問看護ステーションを問題視 スタッフの8割以上を占める事業所が2割以上 事実上の“訪問リハ”に
――厚生労働省
中央社会保険医療協議会総会
厚生労働省は、7月17日の中央社会保険医療協議会(中医協)総会で、理学療法士が多い訪問看護ステーションを問題視した。スタッフの8割以上を占める事業所が2割以上あり、保険上設置が認められていない“訪問リハビリステーション”となっていると指摘。24時間対応をせず、重症度の低い患者のみに対応している可能性があるため、要件の見直しなどに発展する可能性がある。
訪問看護ステーションの数は、この15年でほぼ倍増している。とりわけ2011年以降は右肩上がりで、2011年には5,974だったのが2018年には9,964となった。法人種別としては医療法人と営利法人が多いが、医療法人がほぼ横ばいなのに対し、営利法人は2008年から10年間で約4倍にまで増えている。一方で、看護職員の数は年々減っており、従事者数割合で見ると2002年は91%だったのが、2017年には71%まで落ち込んだ。人数で見ると、5人未満が約62%、5人以上が約38%となっている。
それに比して、理学療法士の数は増加傾向にある。従事者数割合で見ると、2002年に5%だったのが2017年には22%。理学療法士がいない訪問看護ステーションは2009年で63%だったのが、2017年には45.9%となっている。従事者の80%以上を理学療法士が占める事業所は2017年で20.7%。
理学療法士は、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士と同様にリハビリテーション専門職だ。訪問看護ステーションでその割合が多いということは、看護よりもリハビリを重点的に実施している事業所が多いということになる。その仮説を裏付けているのが、24時間対応体制加算の届出割合。理学療法士がいない事業所の78.9%が届出をしているのに対し、スタッフの80%以上を理学療法士が占める事業所は、31.6%しか届出をしていない。つまり、事実上「訪問リハビリステーション」となっている事業所が少なからず存在していることを意味している。裏を返せば、訪問看護ステーションの数が増えているにもかかわらず、24時間対応の訪問看護のニーズに応えられていないともいえよう。
この事実に対して、中医協の診療側委員からは「病院でのリハビリ専門職確保が困難となっている」「健全な姿とはいえず、経営母体と理学療法士の割合との関係も見ていく必要がある」といった声があがっている。訪問看護ステーションは、医療保険、介護保険の双方から給付がなされているサービスであるだけに、地域包括ケアシステムの重要な部分を担うと期待されており、今後何らかの見直しが行われる可能性が高いのではないだろうか。