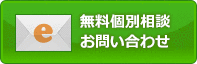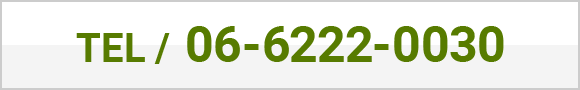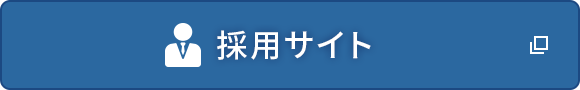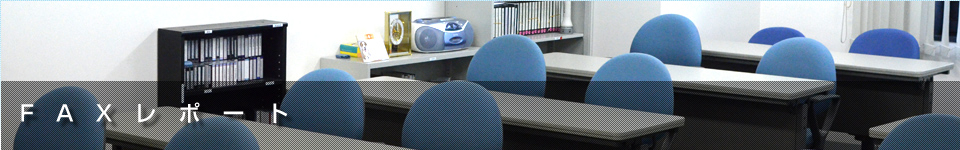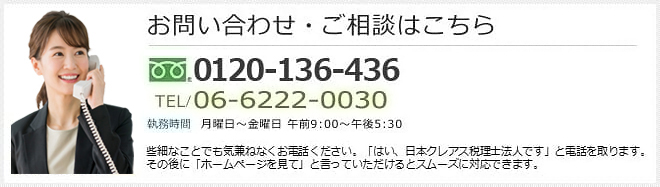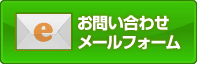ホーム > FAXレポート > 医院レポート > 医療経営情報(2017年3月9日号)
医療経営情報(2017年3月9日号)
◆自治体実施のがん検診、受診率が軒並み低下
胃がん6.3%、肺がん11.2%、大腸がん13.8%
――厚生労働省
3月8日、厚生労働省は「平成27年度地域保健・健康増進事業報告の概況」を発表。がんの部位別死亡数トップの肺がんは11.2%、女性の死亡数トップの大腸がんは13.8%、胃がんは6.3%。子宮頸がんと乳がんはそれよりも多いが、それぞれ23.3%、20.0%と高い数字とは言えない結果となっており、いずれも2014年度(平成26年度)より低下していることがわかった。少なくとも、自治体のがん検診に対する国民の関心が低いことが読み取れる。
市区町村別の受診率分布状況を見ると、その傾向はさらに顕著だ。肺がん検診を50%以上受診しているのは、全国1,737の市区町村に対してわずか80。大腸がんは60で、胃がんに至ってはわずか3にとどまっている。逆に、受診率10%未満の市区町村は肺がん503、大腸がん309、胃がん921となっている。
また、同調査では「平成26年度のがん検診受信者における要精密検査の受診状況」も明らかにされているが、要精密検査を受けた人のうちがんであった人は、調査の対象である5つのがんすべてが1%未満だった。
がんは依然として日本人の死因トップ。それだけに、早期発見・早期治療の重要性はクローズアップされ続けており、もはや常識となりつつある。にもかかわらず、がん検診の受診率が低下し続けているのは、「がんは治る病気」との認識が広まるほど医療が進化していることも理由に挙げられそうだ。実際、2月に国立がん研究センターが発表した部位別のがん10年生存率は約6割となっており、がんに対する恐怖心が薄れているといえるかもしれない。
しかし、同じ国立がん研究センターの発表では、ステージ1だった場合の10年生存率が85.3%と9割に迫る数字を記録しており、やはり早期発見・早期治療が重要であることが改めて浮き彫りとなっている。平成25年に実施された厚生労働省の「国民生活調査」によれば、胃がん、肺がん、大腸がん検診の受診率は4割程度となっており、今回の自治体実施のがん検診受診率とは乖離があるが、いずれにせよ受診率が低いことには変わりがない。検診後に定期的なケアをすることの効能を伝えつつ、受診を推奨していくことが、患者にもっとも近いところにいるかかりつけ医を始め、各医療機関に求められているのではないだろうか。
◆AI活用の診療、「最終的な責任は医師が負うべき」
「医療機器プログラム」として位置づけたい意向も示される
――厚生労働省
3月7日、厚生労働省で「保健医療分野におけるAI活用推進懇談会」の会合が開催され、AI(人工知能)を活用した診療の最終的な責任は医師が負うべきであるとの考えが示された。また、AIプログラムは「医療機器プログラム」として位置づけ、医薬品医療機器法に基づいて安全性・有効性を確保する必要があるとの意向も明らかとなった。
同会合は今年1月から開始されたもので、7日で第3回目。ディープラーニング(深層学習)の登場によって急速な進化を遂げているAIを保健医療分野でいかに活用するか、その効果を明らかにしつつ、開発推進や質・安全性確保のために必要な対応を検討するのが目的だ。肺がん原因遺伝子ENL4-ALKの発見でも知られる国立がん研究センターの間野博行研究所長(東京大学大学院医学系研究科生化学。分子生物学講座細胞情報学分野教授)が座長を務めている。
7日の会合では、間野座長ががんゲノム医療の普及にAIが必須だと説明したほか、難病の診療や創薬、そして在宅医療においてもAI活用の必然性が紹介された。一方で、現状のAIはあくまでも推測を担うツールであり、単独で診断確定や治療方針の決定を行うことはできない。1月に開催された会合でも、AIの推測結果をもとに他のデータベースの情報と統合して医師が解析を行い、治療方針の決定を行っているとの指摘や、AIの推測結果が誤っていた場合は研究者が間違いを指摘して改良を行っているとの意見もあった。
そうした議論を踏まえ、7日の会合では、最終意思決定は医師が行うこと、そしてその責任は医師が負うべきであることを確認。さらに、医師に対してAIについての適切な教育を行っていくことで、安全性を確保することの必要性があることも示された。また、AI技術を用いた医療機器については、早期の実用化が期待される画像を用いた診断分野に着目。どのような評価指標を設定するべきなのかを検討する予定としている。
◆赤字病院の割合は7割以上、自治体病院は9割近くが赤字
常勤職員の平均給与は月額42万7000円 日本病院会調査
――一般社団法人 全国公私病院連盟、一般社団法人 日本病院会
3月6日、一般社団法人全国公私病院連盟と一般社団法人日本病院会は「平成28年病院運営実態分析調査の概要」を公表。赤字病院の割合は72.9%にのぼり、自治体病院の場合は89.0%が赤字であることが明らかになった。
この調査は、両法人が協力して毎年6月に実施しているもの。対象となるのは、全国公私病院連盟の加盟団体に所属している病院と、日本病院会に加盟している病院。3,229の病院に調査協力を依頼した中で、集計対象としたのは919の病院。その内訳は、自治体病院465、その他公的病院217、私的病院199、国立・大学付属病院等が38。
医師1人1日あたりの取扱い患者数は、入院の場合平均4.5人、外来は平均7.6人。医師1人1日あたりの診療収入は、DPC(包括医療費支払い制度)以外の病院だと入院で平均28万円、外来は12万9,000円、DPCの病院での入院は平均22万9,000円、外来は平均10万7,000円となっている。
一方、診療科別の患者1日1日あたりの診療収入は、DPC以外の病院だと入院では心臓血管外科の18万475円が最高額で、最小額は精神科の1万8,762円。外来では放射線科の2万2,117円が最高で、最小額は麻酔科の3,865円。DPC病院の場合も、入院の最高額は心臓血管外科で、最小額が精神科。外来では消化器外科の3万54円が最高額で呼吸器内科、呼吸器外科と続いており、最小額はリハビリ科の4,545円。
また、特徴的なのは医業外収益の少なさ。医業収益を100とした場合、2016年の総収益は102.5。この数字はここ5年間ほぼ横ばいで、病院が医業外の収益を得ることの難しさを物語っている。独立行政法人福祉医療機構が昨年12月に発表した調査結果では、医療以外の事業を実施している医療法人は経営が安定している傾向にあると指摘をしており、赤字病院の割合を考えれば、医業収益のみで黒字を記録するのは極めて難しいのが現状と言えよう。
とはいえ、そうした現状に対して、常勤職員1人あたりの平均給与は月額42万7,000円と決して低くはない。職種別に見ていくと、医師が107万4万円と突出してはいるが、看護師が35万6,000円、准看護師が32万5,000円、看護業務補助者が20万5,000円、薬剤師38万3,000円、その他の医療技術員34万4,000円、事務職員30万4,000円、技能労務員25万4,000円となっており、多職種も決して低水準とは言い切れない数字だ。赤字割合だけを見れば病院経営は明らかに苦境であり、診療報酬割合が適正かどうかも問われる状況ではある。しかし、人件費とのバランスが適正なのかも勘案すると、そもそも病院のスタイルが現在の医療に適しているのかも考慮するべきタイミングに来ているのかもしれない。
◆プレミアムフライデーを活用したがん検診キャンペーンを実施
最先端のPET/CT検査が、ペア受診すると料金割引に
――医療法人社団あんしん会
2月22日、東京・千代田区にある医療法人社団あんしん会 四谷メディカルキューブは、「プレミアムフライデー」を利用して「PET/CT検査」を格安で受診できるプランの提供を同24日からスタートすると発表した。毎年10月に厚生労働省が「がん検診受診率50%達成に向けた集中キャンペーン」を行うなど、がん検診受診率向上が課題となっている現在、注目に値する取り組みだと言えそうだ。
同院が打ち出したプランは、プレミアムフライデーにペアで受診すると通常1人12万円(税別)の受診料が約16%引きの10万円になるというもの。プレミアムフライデーを実施している企業で就労している人を対象としている。
このプランで行うPET/CT検査は、最先端のがん検査だ。細胞の代謝を画像化するPET検査と、全身をX線でスキャンするCT検査を同時に行うことができる。がん細胞は一般的に糖代謝が活発なため、糖に似た構造を持つ専用の薬剤を全身に投与してその代謝を画像化するPET検査でがんの兆候を発見できる仕組みだ。薬の投与後は横になった状態でCTスキャンを受けるだけなので、内視鏡検査などと比べても身体的負担が少ないのが特長だ。特定の臓器に限らず、全身をまんべんなく調べられるのもメリットとなっている。
同院によれば、PET/CT装置を東京都内で初めて導入以降年間9,000件以上の検査実績があるという。所要時間は約2時間半なので、プレミアムフライデーで退社後に受診すれば通常の退社時間と同じくらいに検査を終えることができる仕組み。通常は仕事で忙しくてがん検診を受診する機会がない人に対し、受診機会を提供できるというわけである。
プレミアムフライデーは、その月の最後の金曜日に終業時間を午後3時に早めることで、消費の拡大と働き方改革の双方を目指した経済産業省のキャンペーン。月末の金曜日という繁忙期に、仕事を早く打ち切ることができるかという問題点もあり、一部報道では実施企業はわずか3%という結果も出ているなど賛否両論を巻き起こしているが、少なくとも大きな話題になっていることは間違いない。マーケティング的な意味でも、実際にどの程度の成果が表れるのか興味深いところだ。