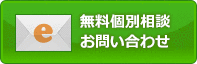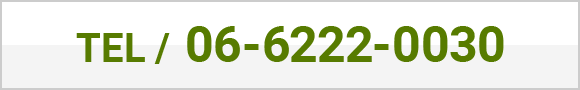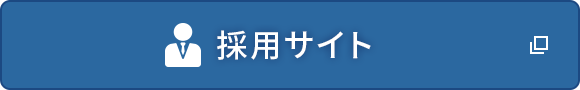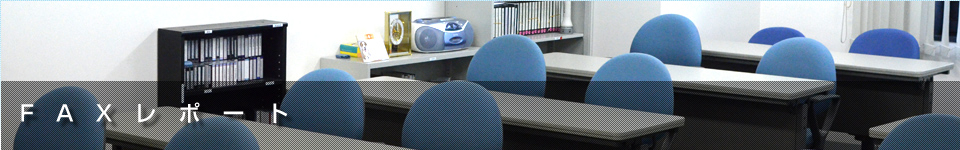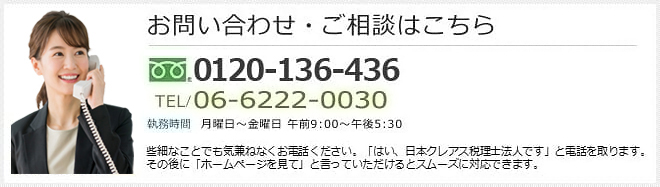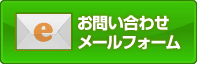ホーム > FAXレポート > 医院レポート > 医療経営情報(2018年3月29日号)
医療経営情報(2018年3月29日号)
◆オンライン医療、日本医師会は消極的な姿勢を示す
「医療アクセスが困難な患者への提供を第一に」
―規制改革推進会議
3月27日、規制改革推進会議は「オンライン医療の推進に向けて~Society5.0のもとで拓ける医療の可能性」をテーマに掲げた公開ディスカッションを開催。委員側は「『一気通貫』で完結できる在宅医療」を目指す姿として挙げ、オンラインでの服薬指導を早急に実現するなど、積極的な推進を訴えた。それに対し、ディスカッションに参加した日本医師会や日本薬剤師会は弊害が多いとして消極的な姿勢を明らかにしている。
日本医師会は、オンライン診療に対する基本的な考えとして「医療へのアクセスが困難な方への提供を第一に」考えるべきと表明。その理由として、医療の本質は患者と医師の信頼関係が基本にあり、あらゆる感覚をフル活用して診察するため対面診療が基本であるとした。そのため、普段から患者を診ているかかりつけ医がオンライン診療を行うことが重要と強調している。さらに、「オンライン診療の光と影」として、バイアグラやED・AGA治療薬などを来院不要で処方する旨を謳った広告が想定されるとし、「安易な営利手段として利用することを考える人がいることも事実」と断じている。
日本薬剤師会は、在宅医療の問題点を挙げつつ、個々の患者に適した調剤設計が欠かせないと説明。オンラインでの服薬指導が困難であることを暗に示した。
一方で、委員側は2025年に65歳以上の割合が30%に達するため、2人未満の現役世代で1人の高齢者を支える時代が到来することを示すとともに、2016年末の医師平均年齢が59.6歳と医療資源が減少傾向にあることを提示。技術が進歩していることを踏まえ、内閣府が掲げる「Society 5.0」(最新技術で社会的課題を解決する新たな社会)を目指すため、新たな医療サービスの可能性を積極的に探るべきとしている。目指すのは、診察から調剤、医薬品配送、服薬までの一連の医療サービスを在宅で利用できる「一気通貫の在宅医療」であり、そのためには、医師によるオンライン診療だけでなく、服薬指導もオンラインに対応するべきだとしている。
ただし、現在は医師法および薬剤師法によって、薬剤師は処方箋の原本がなければ調剤できないことになっている。電子データも原本となり得るという解釈はなされているが、電子処方せんの運用ガイドライン」によれば、電子処方せん引換証と処方せん確認番号を患者が薬局に持参しなければならず、さらに、服薬指導は対面で行う必要があるため、「一気通貫の在宅医療」は制度上成立しない。厚生労働省は昨年11月、国家戦略特区でオンライン服薬指導(遠隔服薬指導)の実証事業実施に関する通知を発出しているものの、未だ開始していないこともあり、業を煮やした委員側が揺さぶりをかけた格好だ。しかし、日本医師会や日本薬剤師会が消極的な態度をとっていることもあり、完全なオンライン医療の実現に至るには多くの壁があることが表面化したといえよう。
◆「急性期医療未提供」の急性期病棟を公表する方針固まる
地域医療構想調整会議の場で「病床機能報告」の確認・検証を
―厚生労働省 地域医療構想に関するワーキンググループ
厚生労働省は、3月28日に開催した「地域医療構想に関するワーキンググループ」で、高度急性期機能または急性期機能を有している報告しながら当該医療をまったく提供していない病棟のデータを公表する方針を固めた。その内容を地域医療構想調整会議で確認・検証していくことになる。
急性期病棟であるとしながら、急性期医療を提供しないというのはおかしなことだが、現実的にそうした病棟は多数存在している。厚労省医政局地域医療計画課の調べによれば、医療法に基づいて義務化されている「病床機能報告」において、高度急性期または急性期病棟と報告しているのは21,262病棟。しかし、「具体的な医療の内容に関する項目」の実施状況を確認すると、「重症患者への対応状況」で全項目該当していない病棟は約83%にものぼる。裏を返せば、少なくとも重症患者に対して十分な対応をしている高度急性期・急性期病棟は約17%、約3,600病棟しかないということになる。
その他の項目も、重症患者対応ほどではないが全項目該当していない割合は決して低くない。「救急医療の実施状況」は約35%、「がん・脳卒中・心筋梗塞等への治療状況」は約25%、「幅広い手術の実施状況」は約18%、「全身管理の状況」は約17%。これは厚労省による粗集計のため、どの病棟がどの項目に対応しているかは明らかではないが、数字だけを見れば、急性期病棟を謳いながら急性期医療に対応していない病棟はかなりの数になってしまう。
一方で、「病床機能報告」の基準が曖昧なのも確かだ。病棟が担う医療機能のいずれか1つを選択して報告することになっているため、実数と乖離している現象も生じている。集計結果だけを見れば、回復期を担う病床数が大幅に不足していると誤解させる数値も出てしまうため、制度の早急な見直しが求められている。
そこで遡上にのぼっているのが、奈良県や佐賀県で導入している方式だ。奈良県では「50床あたりの手術+救急入院件数1日2件」という独自基準で急性期病棟を判断しており、超過した場合は「重症急性期中心」、そうでない場合は「軽症急性期中心」と報告するようにしている。佐賀県では、「地域包括ケア入院医療管理料を算定する病床数」「調整会議で回復期への転換協議が整った病床数」は、回復期とみなし、急性期病棟のうち「平均在棟日数22日超」の病棟は、回復期病床数見込みの判断材料としている。これらを取り入れて2018年度の病床機能報告の基準や項目が見直される可能性が高いため、医療機関は議論の推移を見守りつつ、齟齬がない報告をする必要がありそうだ。
新専門医制度、専攻医の採用状況を公表
機構側は「都市部への集中は抑制」と強調
――厚生労働省 今後の医師養成の在り方と地域医療に関する検討会
3月27日、厚生労働省で「今後の医師養成の在り方と地域医療に関する検討会」が開かれ、一般社団法人日本専門医機構から2018年度からスタートする新専門医制度の「専攻医の採用状況」が提示された。懸案となっていた「医師の偏在化」問題について、日本専門医機構は「都市部への集中は抑制されている」と説明。しかし、採用状況データを確認した同検討会の構成員からは「東京への医師集中は明らか」といった意見が続出している。
新専門医制度は、昨年10月10日から登録が開始され、3月5日までに8,394人が採用されている。新専門医制度整備指針では、都市部への集中を抑制するため東京・神奈川・愛知・大阪・福岡の5都府県は過去5年の専攻医採用実績の平均値を超えない採用者数にするとしており、定員の上限を設定。実際、平均値を超えない採用者数に止めることには成功している。
しかし、データの見方によっては、逆に都市部集中が進んでいると捉えられることも確か。たとえば、東京に勤務している専攻医は全体の約21%を占めている。また、2016年度の初期臨床研修医採用状況と今回の採用状況を比較すると、関東ブロックで占める割合は34.9%から37.3%に上昇。新専門医制度での専攻医は初期臨床研修医と同様のポジションにあるため、事実上関東ブロックへの集中が進んでいると考えられる。そうしたことを踏まえれば、医師が集中しがちな5都府県の定員上限数を今後見直す可能性もありそうだ。
従来、専門医資格は乱立状態にあり、質のばらつきが指摘されてきた。各学会が独自に認定していることも原因だったため、厚生労働省は2011年から専門医制度の見直しを検討し、2014年5月に学会に対して中立的な立場となる第三者機関として日本専門医機構を設立。新たな専門医制度の構築を進めてきた。新専門医制度は、19領域を持つ「基本領域専門医」と29領域を持つ「サブスペシャリティ領域専門医」の2つに大別。専門医資格を希望する場合は、医学部を卒業後に2年間の臨床研修を受け、さらに3年以上の研修を受ける必要がある。
◆経済財政諮問会議、2020年度時点の医療費試算を公表
「地域差半減」の実現で2,700億円程度の抑制を見込む
――経済財政諮問会議
政府は3月29日に経済財政諮問会議を開き、2020年度時点の医療費試算を公表。「地域差半減」の取り組みが実現することを前提に、国・地方の合計で2,700億円程度、保険料3,400億円程度の抑制効果を見込んでいるとした。同様に地域差縮減に取り組んでいる介護費に関しては、国・地方の合計で300億円程度、保険料300億円程度を見込んでいる。
医療費抑制の取り組みは、社会保障費の自然増を抑えるために避けることができないのが現状だ。 昨年9月に発表された2016年度の概算医療費は14年ぶりに減少しているが、その減少幅は0.4%程度とわずか。高額がん治療薬オプジーボの薬価を半額に緊急値下げしたにもかかわらず、大した効果は表れていない。金額としても41兆2,685億円と依然として40兆円を超えており、厚生労働省は「増加傾向に変化はない」との見通しを明らかにしている。
構造的な見直しももちろん実施。今年度の診療報酬改定で入院基本料の改革を行ったほか、オンライン診療(遠隔診療)の本格導入を開始し、ジェネリック医薬品の推進にも力を注いでいる。一方で、即効性を期待して1月23日の経済財政諮問会議で今年前半の主要検討課題に挙げているのが「地域差半減」である。公的な医療サービスは全国一律価格となっているものの、入院期間の長さや外来受診回数、薬剤使用量などで地域差が生じているからだ。
しかし、実情を踏まえると地域差は簡単に解消するとは考えにくい。医療機関が少ない地域では、通院に多大な負担がかかるため入院期間が長引かざるを得なかったり、一度の外来受診で多くの検査を実施したりせざるを得ない。都道府県よりも市区町村別の地域差が大きいのはそのためだ。ICT環境を迅速に整備して、検査や投薬の重複を防ぐなど効率的な医療を促すのが有効と考えられるが、ドラスティックな効果を期待するのは難しい。政府もそのあたりの事情は十分に理解しているのか、公表された試算には「直線的に実現すると仮定」と前提条件をつけている。今回の諮問会議では、高齢者数がピークを迎える2040年頃を見据えて「社会保障給付や負担の姿を幅広く共有することが重要」として、民間議員が社会保障の将来推計を早急に示すべきと政府に求めたが、「2,700億円抑制」という試算がそれに対するひとつの回答であり、ひとまずの数値目標として示したものと受け止めたほうが良さそうだ。