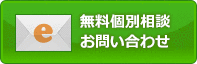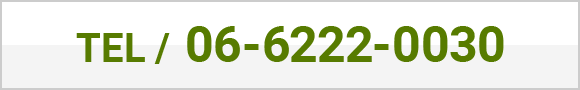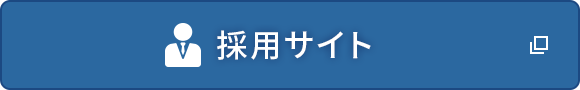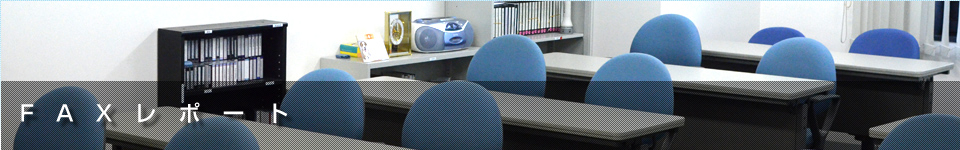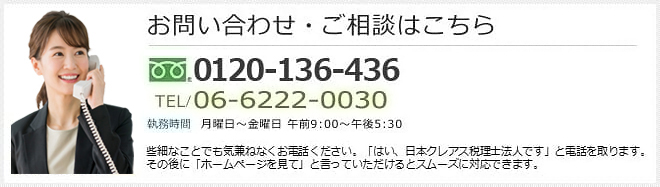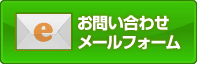ホーム > FAXレポート > 医院レポート > 医療経営情報(2018年2月8日号)
医療経営情報(2018年2月8日号)
◆来年度診療報酬改定の内容が決まる
再編・統合される入院基本料は旧「7対1」から移行しやすい点数に
―厚生労働省 中央社会保険医療協議会総会
厚生労働相の諮問機関である中央社会保険医療協議会は、2月7日に加藤勝信厚労相へ来年度診療報酬の改訂案を答申。個別の点数を含め、改定の内容が確定した。入院基本料は旧「7対1」に該当する「急性期一般入院料1」が据え置きの1,591点、旧「10対1」との中間的な評価として新設された「急性期一般入院料2」は30点減の1,561点、「急性期一般入院料3」は100点減の1,491点、旧「10対1」に該当する「急性期一般入院料4~7」は1,387点、1,377点、1,357点、1,332点と据え置かれた。旧「7対1」から下位区分への移行をスムーズにするための点数設計がなされたといえる。
入院基本料は、今回の改定の焦点のひとつ。今まで看護配置基準を中心とした切り分けで「7対1」「10対1」と呼ばれていたのを再編・統合。診療実績をもとに切り分ける「急性期一般入院料」として見直され、7段階に区分された。
細かい区分となったのは、「10対1」に比べて200点も高かった「7対1」の急激な増加が背景にある。政府としては、膨張を続ける医療費を抑制するためにも、「7対1」に一極集中している状況を変える狙いがあった。急性期に医療機関が集中することで、回復期や慢性期の体制が不十分となって対応できない医療ニーズが生じる可能性があるほか、「7対1」の中には、稼働率アップのため軽症者を受け入れているところがあるのも、「10対1」への移行促進を急ぎたい理由だ。
しかし、200点の格差があることから、厚労省は200床以上の病院が「7対1」から「10対1」へ移行すると年間1億2,000万円の減収となると試算。そこまで減収すると経営に深刻な影響を及ぼしかねないため、「7対1」と「10対1」の中間となる評価を2区分用意し、移行への影響を最小限にとどめた。
一方で、旧「7対1」となる「急性期一般入院料1」の要件は厳格化。重症患者割合を従来の25%から30%に引き上げ、「重症者のための医療機関」であることをより明確化させた。必然的に、旧「7対1」にとどまれる医療機関は減少するため、その受け皿となる中間評価の「急性期一般入院料2」および「急性期一般入院料3」の点数が注目されていた。結果、「急性期一般入院料2」は30点減、「急性期一般入院料3」は100点減少となったため、重症患者割合が30%に届かない医療機関も、移行を受け入れやすくなったといえよう。移行せざるを得ない医療機関は、減収を最小限に抑える方策を練る必要がありそうだ。
◆入院生活や退院後の支援内容の事前説明に新加算「入院時支援加算」
早期の在宅復帰を促すとともに、地域包括ケアシステムの構築を促進
―厚生労働省 中央社会保険医療協議会総会
2月7日に確定した2018年度診療報酬改定。入院医療では、新たに「入院時支援加算」が設けられた(200点、退院時1回)。入院生活や退院後の支援内容を事前に説明することで算定することが可能だ。早期の在宅復帰を促すことで医療費を抑制するとともに、退院後のフォロー体制をより手厚くすることで、介護施設などを含めた地域包括ケアシステムの構築を促す狙いがある。
これまで、退院前の患者・家族との面談や多職種が集まるカンファレンスの実施、ケアマネジャー(介護支援専門員)との調整などは「退院支援加算1~3」として評価されてきた(1は一般病棟600点、療養病棟1,200点。2は一般病棟190点、療養病棟635点。3は1,200点)。
まず、実態として退院時だけでなく入院早期からの支援を評価していることから、名称を「入退院支援加算」に変更。そして、入院時により詳しくオリエンテーションを行い、患者情報やリスクアセスメントを実施させるため、「入院時支援加算」を新設。患者にとっては、入院中にどのような治療プロセスがあるのかをイメージできるため安心できるメリットがある。
なお「入院時支援加算」の算定を受けるには、「入退院支援加算」の届出を行う必要があるほか、「入退院支援加算」の施設基準の人数以外に入院前支援の担当者を配置し、地域連携を行うための十分な体制を整備する必要がある。
一方、「入退院支援加算」の算定要件である「退院困難な要因」の対象に、虐待や生活困窮などで入院早期から福祉関係機関との連携が必要な小児も追加された。それに伴い、小児専門の医療機関や病棟の場合は、算定要件である「介護支援等連携指導料の算定件数」の要件が緩和されるほか、小児加算(200点)も新設されるので注意したい。
◆「かかりつけ医」の初診料、実質3割引き上げ
80点の「機能強化加算」を新設 患者への広報が必要か
――厚生労働省 中央社会保険医療協議会総会
2月7日に確定した2018年度診療報酬改定では、「かかりつけ医」の初診料が手厚く評価されることとなった。80点の「初診料 機能強化加算」が新設され、実質的に初診料が3割引き上げられることとなる。
「初診料 機能強化加算」の算定要件となるのは、地域包括診療料などを届け出ている診療所もしくは200床未満の保険医療機関(※)。外来医療において、大病院とかかりつけ医との適切な役割分担を図り、機能分化を進めるのが目的だ。
また、高齢者の増加に伴い、初診の診療時間が長引く傾向が強まっているのも、今回の引き上げを後押ししている。1人当たりの診療時間が長くなれば、対応できる患者数を増やすことができないのは明らか。かといって、機能分化を推し進めている以上、かかりつけ医は的確かつ質の高い外来診療を行う必要がある。診療所経営の健全性を確保するため、やむを得ず初診料の加算を決めたということだろう。
ただし、この引き上げは患者の自己負担増にもつながる点に注意したい。実質的に3割近く初診料が高くなるため、わざわざ高い診療所に行くよりも、より安く済む病院を選ぶといった形で、患者の「病院選び」が変わる可能性すらある。というのは、今回の診療報酬改定で、400床以上の病院で紹介状なしに受診すると初診時に5,000円以上が徴収されることが決まったが、200床以上400床未満は徴収が義務付けられていないからだ。制度上は、200床以上400床未満の病院だと「患者負担が増えず」「定額徴収されることもない」ということになる。実際は、200床以上の病院は多くが定額徴収を行っているため、大きな影響が出ることはないだろうが、患者に混乱を与える可能性は否定できない。かかりつけ医機能を有する診療所や病院は、自己負担が増えることを患者にしっかり伝える必要があるだろう。考えようによっては、なぜ負担額が増えるのかを説明することで、「それでもかかりつけ医を受診することのメリット」を啓蒙するチャンスともいえる。患者とのコミュニケーションを深める好機と捉え、対策を講じていくことが診療所にとって重要となるのではないだろうか。
※初診料 機能強化加算の算定要件
地域包括診療加算、地域包括診療料、認知症地域包括診療加算、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院に限る)、施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院に限る)を届け出ている保険医療機関(診療所または200床未満のみ)
◆遠隔診療の評価が新設 「オンライン診療料」など
6カ月の通院後に算定可能と現実的には機能しにくい形に
――厚生労働省 中央社会保険医療協議会総会
2月7日に確定した2018年度診療報酬改定では、遠隔診療に対する評価も新設された。「オンライン診療料」(1月につき70点)、「インライン医学管理料」(1月につき100点)、「在宅時医学総合管理料 オンライン在宅管理料」(1月につき100点)、「精神科在宅患者支援管理料 精神科オンライン在宅管理料」(1月につき100点)がそれだ。しかし、「初診から6カ月間、毎月同一医師による対面診療を実施」する必要があるほか、3カ月以上は算定対象外となるなど、現実的には機能しにくい形となった。
遠隔診療とは、スマートフォンやタブレット、パソコンなどを媒介とし、テレビ通話やスカイプなどで行う診療のこと。従来は、離島やへき地の患者などを除いて禁止されていたが、2015年8月に事実上解禁されている。しかし、診療報酬上の評価には該当するものがなく、初診料および再診料の請求しかできないとあって、なかなか普及してこなかった。
一方、医療費は40兆円を突破しており、外来診療の頻度を減らした「効率的な医療」の実現が喫緊の課題となっている。とりわけ、糖尿病などの生活習慣病治療は外来診療のみだとコストがかかるため、遠隔診療へシフトさせて医療費を削減しようとしてきた。昨年4月の未来投資会議では、安倍晋三首相が2018年度診療報酬改定で評価すると明言しており、その要件や点数がどうなるか注目されていた。
しかし、今回定められた要件は、遠隔診療の促進につながるとは言い難い。むしろ、医療機関にとっては導入するメリットが非常に薄いのではないだろうか。対面診療が前提となっているのはともかく、月1回の受診を6カ月続けたのちに遠隔診療に切り替えるというのは現実的ではない。しかも、遠隔診療に切り替えても算定できるのは3カ月のみ。さらに、「オンライン診療料」を算定できるのは1月につき70点だから、1カ月以内に2回遠隔診療を行うことは診療報酬上無意味ということになる。「1月当たりの再診療等(電話等による再診は除く)およびオンライン診療料の算定回数に占めるオンライン診療料の割合が1割以下」との施設基準も設けられており、実質的には緊急時のオプションとして遠隔診療が認められたに過ぎない。効率的な医療につながる内容とも思えず、医療機関にとっては、新たにシステムを導入する価値があるかどうか疑問だ。遠隔診療のガイドラインの策定も行われているが、2018年が「遠隔診療元年」となる可能性は低いかもしれない。