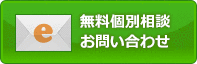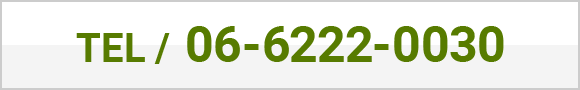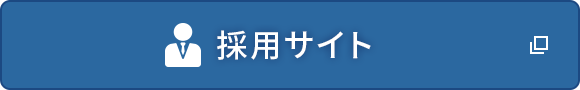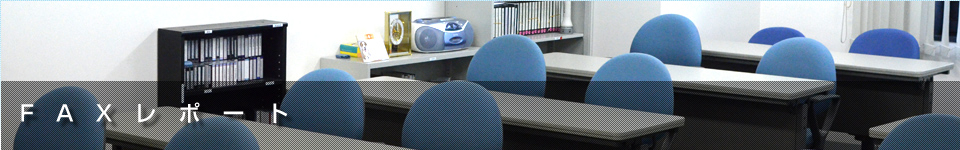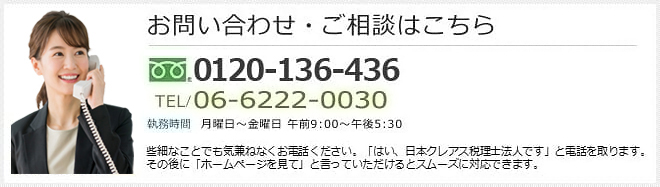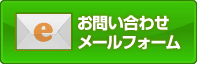ホーム > FAXレポート > 医院レポート > 医療経営情報(2019年8月29日号)
医療経営情報(2019年8月29日号)
◆ がん生存率、「3年」「5年」とも上昇 国がん調査 前立腺、乳はともに90%以上 膵臓の5年生存率は低下
――国立研究開発法人国立がん研究センター
国立がん研究センターは、8月8日にがん生存率(※)の調査結果を公表。3年生存率は全体で72.1%、5年生存率は66.1%といずれも前回調査よりも上昇したことがわかった(昨年発表された前回調査では、3年生存率が71.3%、5年生存率が65.8%だった)。部位別に見ると、前立腺がん、乳がんは3年生存率、5年生存率ともに90%以上。一方で、難治性がんの代表格とされる膵臓がんは5年生存率が前回調査よりも下がっており、新たな治療法や早期発見のための手立てが改めて求められる結果となった。
調査は、全国のがん診療連携拠点病院を対象に実施。5年生存率は2009~2010年にがんと診断された患者のデータを、3年生存率は2012年にがんと診断された患者のデータをもとにしている。3年生存率は286施設33万9,376例(前回調査は268施設30万6,381例)から、5年生存率は277施設56万8,005例(前回調査は251施設50万1,569例)から集計された。3年生存率は昨年に続いて2回目、5年生存率は4回目の発表となる。
全体の生存率が上がっているのは、画期的な治療薬や、がんだけに放射線を当てられる機器、侵襲性の低い手術を可能とするロボット医療などの登場による医療の進化が影響している。ステージが進むにつれてどの部位でも生存率が下がっていることからも、早期発見・早期治療が重要なのは間違いないため、がん検診の実施率向上も生存率アップに貢献しているといえよう。それだけに、前出の膵臓がんのような難治性がん対策の遅れが際立つ。
膵臓がんが難治性なのは、初期段階で症状が出にくいため早期発見しにくいのが理由だ。胃の後ろの深部にあるため検査しても発見しにくく、近くに重要な臓器や血管があることから肺や肝臓などに転移しやすい。高圧な電流でがん細胞を破壊できることから、切除不能ながんに適応できる「ナノナイフ」を保険適用するなどの対策が急がれる。そのためにも、部位別の生存率データを公表している意味は大きい。
国立がん研究センターもそのことは理解していて、今年の3年生存率の集計部位に比較的患者数の少ない喉頭がん、胆のうがん、腎がん、腎盂尿管がんを追加。その結果、喉頭がんはI期が96.0%、II期が90.2%と、放射線治療が有効な段階では生存率が高いことがわかった。腎がん、腎盂尿管がんも、I期、II期では90%以上となっている。膵臓がんととも難治性とされる胆のうがんは33.4%だったが、根治切除が可能なI期では91.1%、II期では77.4%となっており、早期発見の重要性が数字の上でも明らかとなった。胆のうがんも膵臓がんと同様に初期での自覚症状がなく、早期診断も難しいとされるため、治療法のみならず効果的な診断方法の開発などが求められよう。
◆ 四病協、13項目にわたる要望書を厚労相に提出
医療機関の消費税課税や自由診療に対する軽減税率適用など
――四病院団体協議会
四病院団体協議会(四病協)は8月9日、根本匠厚生労働相に「令和2年度税制改正要望の重点事項について」と題した要望書を提出。全13項目にわたる内容で、医療機関を原則として消費税課税にすることや、自由診療に対する軽減税率適用などが盛り込まれている。四病院団体協議会は、「日本病院会」「全日本病院協会」「日本医療法人協会」「日本精神科病院協会」で構成される民間病院を中心とした病院団体協議会。
現在、診療報酬は非課税だが、医療機関を運営する際には医療機器や医薬品、医療材料や消耗品などの購入が欠かせない。これらは消費税を上乗せした金額で購入しているが、仕入税額控除を受けることができないため、診療報酬は消費税相当額を補填した設計をしていることになっている。
しかし、実際は補填が十分でないケースが散見されるほか、医療機関種別ごとに補填のばらつきが生じているのが実態だ。厚生労働省は、医療機関種別によってばらつきがあることを認めつつ、全体の補填率は100%以上としていたが、昨年7月に計算ミスがあったことが明らかとなった。中央社会保険医療協議会の診療報酬調査専門組織「医療機関等における消費税負担に関する分科会」が公表した「消費税率8%への引上げに伴う補てん状況把握結果」によれば、全体の補填率は92.5%で、病院の補てん率は85.0%だった(診療所は111.2%、歯科診療所は92.3%、保険薬局は88.3%)。
これを受け、「平成31年度税制改正大綱」には「必要に応じて診療報酬の配点方法の見直しなど」が望まれると明記された。しかし、四病協は「画一的補填方式には個々の医療機関の仕入税額が考慮されていない」として、「どれほど補填方法を精緻化しようとも、税負担の不公平性は解消し得ない」と断じるとともに、消費税非課税制度と診療報酬などの公定価格制度は目的が異なるため、診療報酬改定で消費税問題をカバーする方法には限界があると指摘。抜本的解決のため、診療報酬に対する消費税を原則として課税化し、仕入税額控除を認めるべきだと迫っている。
なお、自由診療に対する軽減税率適用については、「医療機関は行政サービスを享受するというより、行政が行うべき公共的サービスを自ら担っている側」と要望する理由を説明。その他、「医療法人の法人税率軽減と特定医療法人の法人税非課税」「介護医療院への転換時の改修等に関する税制上の支援措置の創設」「中小企業関係設備投資減税の医療界への適用拡大」「病院用建物等の耐用年数の短縮」なども要望している。
四病協は以前から消費税非課税を見直すべきとの主張をしており、厚労省および政府がそれを斟酌するとは考えにくい。しかし、消費税分の補填不足が明らかになるなど、診療報酬の設計に問題があることを改めて指摘する意味は少なくない。四病協が主張するような抜本的解決にはならないにしても、なんらかの特例措置を用意するなどの折衷案が出されるか注目したいところだ。
◆ ロタウイルスワクチンの定期接種化、費用対効果が「良好ではない」 リスクベネフィットの観点では問題なし 年内に見直しの論点を整理
――厚生労働省
厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会
厚生労働省は8月7日、厚生科学審議会の予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会で、ロタウイルスワクチンについての「ワクチン評価に関する小委員会」からの報告を取りまとめた。リスクベネフィットの観点では問題はないとしながら、費用対効果は「良好ではない」とし、定期接種化には否定的な見方を示している。
ロタウイルスワクチンは、非常に感染力の強いロタウイルス下痢症の発症リスクを低下させるとされる。「ワクチン評価に関する小委員会」は、代表的なロタウイルスワクチンであるロタリックスおよびロタテックに関する研究結果として、ロタウイルス下痢症の発症防止効果は、「高所得国においては約90%、低所得国で約50%その中間に属する国では約70%」とした。また、日本のヒトロタウイルスに起因する急性胃腸炎の95%以上で有効性が「実証または示唆」されているとし、ロタリックスもロタテックも同等の有効性があるとした。
海外では、ロタウイルスワクチンの接種後、腸重積症の発症リスクが増加するとの報告もある。同ウイルスの第一世代であるロタフィールドが疑われ、市場から撤収されたが、ロタリックスおよびロタテックは、大規模な治験を実施した結果、「腸重積症の発生頻度の有意な上昇」は認められなかった。これらを踏まえ、「腸重積症の発症率が増加するリスク」は否定できないものの、大きなものではないとの考えを示している。さらに厚労省は、腸重積症などのリスクと予防効果によるベネフィットを比較した結果、ベネフットがリスクを大きく上回るとの判断も示した。
ただし、ロタウイルスのワクチン価格は高額だ。「ワクチン評価に関する小委員会」の試算によれば、ロタリックスは1回1万800円(2回接種が必要なので計2万1,600円)、ロタテックは1回6,152円(3回接種が必要なので計1万8,456円)。行政としての費用対効果を考慮すると、節減できる社会的なコストよりも接種費用のほうが高くつくと指摘している。
この厚労省の姿勢は、ワクチンを製造販売する製薬会社への牽制の意味もあるだろう。ロタリックスはグラクソ・スミスクライン、ロタテックはMSDが製造販売承認を取得しているが、「接種にかかる費用が全体で少なくとも4,000円程度低下すれば」費用対効果が期待できるとの意見も提示しており、販売価格の引き下げを迫っているとの見方もできよう。年内は予防接種に関する施策の現状についての意見交換や、学会・関係団体および自治体からのヒアリングをして論点整理を行い、年明け以降に提言をとりまとめるスケジュールを示していることから、来年1月末から2月あたりにはある程度の目途がつくと考えてよさそうだ。
◆ 医療事故調査制度、医療機関側の理解が進まず 「医療事故報告の判断」の相談が未だ多いのが現状
――一般社団法人日本医療安全調査機構
日本医療安全調査機構は8月9日、今年7月の医療事故調査制度の現況を公表。医療事故発生の報告、院内調査結果報告はともに32件ずつだった。一方、相談件数は171件で、「医療事故報告の判断」に関する相談は98件(医療機関16件、遺族等82件)、「手続き」に関する相談は38件(医療機関37件、遺族等1件)で、遺族側はともかく医療機関にも医療事故調査制度の内容理解が進んでいない現状が浮き彫りとなった。
医療事故調査制度は2015年10月にスタート。予期しなかった死亡・死産事故が調査対象で、医療機関は事故が発生したら、日本医療安全調査機構の「医療事故調査・支援センター」に報告する義務がある。「医療事故調査・支援センター」は、医療法の規定に基づき厚生労働大臣が定めた団体。
医療事故調査制度が開始した当初は、毎年1,000~2,000件程度の報告件数があるとの見込みだった。しかし、スタートから4年近く経過した現在までに報告された医療事故は1,452件。想定よりかなり少ない状態だ。これは、前述したように制度の内容が理解されていないのが原因と思われるが、制度自体にも欠陥があるのではないか。
というのは、「予期しない死亡事故」の定義が曖昧なため、報告の必要がないと考えられているケースも想定されるからだ。また、医療事故であることを認めることによる不利益を回避したいとの思惑も透けて見える。実際、昨年3月に日本医療安全調査機構が公表した2017年のデータによれば、患者が死亡してから日本医療安全調査機構に報告するまでの平均日数は57.2日。平均で約2カ月かかっているわけで、遺族からの要請を受けてから動いていると推測される。もう少し明確な基準を示すなど、医療機関側がすぐに動かざるを得ない環境を整備することで解消できる課題だろう。
また、この状況を作り出している遠因は、一般的な認知度が深まっていないことにもありそうだ。遺族側から生存事例に関する相談が寄せられているのも、その表れといえる。適切な“監視体制”による緊張感の創出は、医療事故の防止だけでなく、医療の質の向上にもつながる。厚生労働省は、そのあたりを踏まえた環境整備を進めるべきではないか。